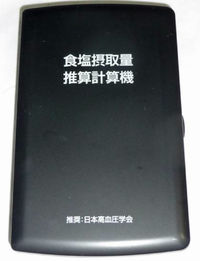2012年10月31日
インフルエンザウィルス感染症の出席停止期間
毎年、この時期になると話題となる「インフルエンザウィルス感染症」ですが、インフルエンザにおける出席停止期間については、「学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令(平成24年文部科学省令第11号)」が、2012年4月2日に施行されました。
インフルエンザの出席停止期間の基準は、従来「解熱した後2日を経過するまで」とされていました。今回の改正では、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」となりました。
ただし、幼稚園に通う幼児については、「保育所における感染症対策ガイドライン」(平成21年8月厚生労働省)において、幼児では年長の児童生徒に比べて長期にわたってウィルス排泄が続くという事実に基づき、登園基準を「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後3日を経過するまで」と改正されました。
改正要因としては、ヒトでの感染実験において、インフルエンザウィルス感染を起こさせた後、概ね2日目に発症(発熱)し、さらに5日を経過した後(感染を起こさせて後7日経過した後)になると、ウィルスがほとんど検出されなくなるという結果があること。さらに、発症後に抗ウィルス薬を投与された場合、投与されなかった場合のウィルス残存率の調査において、薬剤種別及びウィルス亜型によりウィルス減量の速度に差があるものの、発症(発熱)した後5日を経過したところで、ウィルスの体外への排出がほぼなくなる等の報告を踏まえて、出席停止期間は、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで(幼児は、解熱した後3日を経過するまで)」と改めるのが適当とされました。
オセルタミビル(タミフル)、ザナミビル(リレンザ)等をはじめとする抗インフルエンザウィルス薬の投与が一般的となったことも改正に影響を及ぼしています。当院のような市中クリニックにおいてもインフルエンザウィルス感染症の有無について、迅速評価可能となり、早期治療対応できる様になりました。この結果、抗インフルエンザウィルス薬投与によって、感染力が消失していない段階においても解熱効果がえられており、従来の「解熱した後2日を経過するまで」を基準にした停止期間では、感染症の蔓延予防という目的が達成できないことになります。
抗インフルエンザウィルス治療薬が普及し、ウィルスの排出は続いていても熱だけは早期に下げられるようになった一方で、感染者は発症直前から発症後3~7日ほどの間はウィルスを排出するとの知見も出されています。
当院においては、以上のことを踏まえ、インフルエンザウィルス感染者の学校出席停止期間や、就労されている方の職場復帰までの自宅安静療養期間については、重篤な合併症を発症していない限り、受診治療開始後7日間程度としています。
〜百日咳と流行性耳下腺炎も改正されました〜
今回の「学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令(平成24年文部科学省令第11号)」では、百日咳と流行性耳下腺炎も見直しされました。
百日咳の出席停止期間を 従来の「特有のせきがきえるまで」から 「特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで」
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)の出席停止期間を 従来の「耳下腺の腫れが消えるまで」から 「耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後(腫れが出た後)5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで」とされました。
関連資料
学校保健「学校感染症による出席停止」
厚生労働省「学校保健安全法施行規則改正に関する報告書」
学校において予防すべき感染症の指導参考資料の作成協力者会議
Hayden FG,Fritz RS,Lobo MC,Alvord WG,Strober W,Straus SE. Local and systemic cytokine response during experimental human influenza A virus infection J.Clin.Invest 101 : 643-649
インフルエンザの出席停止期間の基準は、従来「解熱した後2日を経過するまで」とされていました。今回の改正では、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」となりました。
ただし、幼稚園に通う幼児については、「保育所における感染症対策ガイドライン」(平成21年8月厚生労働省)において、幼児では年長の児童生徒に比べて長期にわたってウィルス排泄が続くという事実に基づき、登園基準を「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後3日を経過するまで」と改正されました。
改正要因としては、ヒトでの感染実験において、インフルエンザウィルス感染を起こさせた後、概ね2日目に発症(発熱)し、さらに5日を経過した後(感染を起こさせて後7日経過した後)になると、ウィルスがほとんど検出されなくなるという結果があること。さらに、発症後に抗ウィルス薬を投与された場合、投与されなかった場合のウィルス残存率の調査において、薬剤種別及びウィルス亜型によりウィルス減量の速度に差があるものの、発症(発熱)した後5日を経過したところで、ウィルスの体外への排出がほぼなくなる等の報告を踏まえて、出席停止期間は、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで(幼児は、解熱した後3日を経過するまで)」と改めるのが適当とされました。
オセルタミビル(タミフル)、ザナミビル(リレンザ)等をはじめとする抗インフルエンザウィルス薬の投与が一般的となったことも改正に影響を及ぼしています。当院のような市中クリニックにおいてもインフルエンザウィルス感染症の有無について、迅速評価可能となり、早期治療対応できる様になりました。この結果、抗インフルエンザウィルス薬投与によって、感染力が消失していない段階においても解熱効果がえられており、従来の「解熱した後2日を経過するまで」を基準にした停止期間では、感染症の蔓延予防という目的が達成できないことになります。
抗インフルエンザウィルス治療薬が普及し、ウィルスの排出は続いていても熱だけは早期に下げられるようになった一方で、感染者は発症直前から発症後3~7日ほどの間はウィルスを排出するとの知見も出されています。
当院においては、以上のことを踏まえ、インフルエンザウィルス感染者の学校出席停止期間や、就労されている方の職場復帰までの自宅安静療養期間については、重篤な合併症を発症していない限り、受診治療開始後7日間程度としています。
〜百日咳と流行性耳下腺炎も改正されました〜
今回の「学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令(平成24年文部科学省令第11号)」では、百日咳と流行性耳下腺炎も見直しされました。
百日咳の出席停止期間を 従来の「特有のせきがきえるまで」から 「特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで」
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)の出席停止期間を 従来の「耳下腺の腫れが消えるまで」から 「耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後(腫れが出た後)5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで」とされました。
関連資料
学校保健「学校感染症による出席停止」
厚生労働省「学校保健安全法施行規則改正に関する報告書」
学校において予防すべき感染症の指導参考資料の作成協力者会議
Hayden FG,Fritz RS,Lobo MC,Alvord WG,Strober W,Straus SE. Local and systemic cytokine response during experimental human influenza A virus infection J.Clin.Invest 101 : 643-649
Posted by 松山医院大分腎臓内科 at 21:01
│医院について