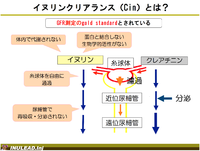2012年06月10日
塩を減らそうプロジェクト
慢性腎臓病の治療において、血圧を適正値に管理することは重要です。
日本腎臓学会は「CKD診療ガイド2012」を6月1日に発表しました。
慢性腎臓病患者の目標血圧管理も改訂されました。
これまでは「蛋白尿1g/日以上の場合、目標血圧は125/75mmHg未満」でしたが、
「全CKD患者の診察室目標血圧が130/80mmHg以下」に改訂されています。
◇降圧薬の第一選択は、糖尿病および0.15g/gCr以上の蛋白尿を有する患者では、
ACE阻害薬・ARBを第一選択。
◇蛋白尿が0.15g/gCr未満で、糖尿病でない患者の場合、
降圧薬の種類は問わないこととしています。
◇高度蛋白尿(0.50g/gCr以上)を呈する若年や中年患者では、
ACE阻害薬・ARBの使用を勧めています。
◇高齢者の場合は慎重な降圧を求め、140/90mmHgを暫定目標に降圧し、
腎機能悪化や虚血症状がないことを確認後、130/80mmHg以下へ降圧としています。
そして、食事療法は、慢性腎臓病管理の中で重要な要素となります。
基本事項は、
① 必要エネルギーを確保する(*1)
② たんぱく質を控える(*2)
③ 塩分を控える(食塩摂取量の基本は3g/日以上6g/日未満)
④ カリウムを控える(*2)
*1 肥満がある場合は、制限します。
*2 腎機能の低下の程度(病期)により指示量が異なります。
今回は、上記①〜④の項目の中で③塩分を控えるについて確認してみます。
日常診療で管理栄養士に塩分制限6g/日未満!の指示をし、栄養指導を行なっています。
外来では、24時間蓄尿検査を実施し、適切な食事管理が実行できているか確認します。
WEBサイト上では、「塩を減らそうプロジェクト」という団体が設立されています。
2010年1月に設立、代表顧問は、荒川規矩男先生(福岡大学 名誉教授、日本高血圧協会 理事長)です。余談ですが、荒川先生には、福岡大学において臨床及びベッドサイド講義で大変お世話になりました。
プロジェクトでは、治療の基本である、「一、に減塩、二、に運動、三、に薬物治療」をもとに、塩の摂取を減らすとともに、塩を体外に排出することで、体内減塩化を図ることの重要性を啓発しています。
日本では約4,000万人いるといわれる高血圧は、サイレントキラー ※であるために早期治療が行なわれず、放置された終末像としては、脳卒中・心筋梗塞・人工透析を必要とする慢性腎臓病などを合併します。高血圧を引き起こす主な要因の一つに、食塩の過剰摂取が挙げられています。世界的に食塩摂取量が多い日本人は、減塩のための工夫が必要です。
※ サイレントキラー:“沈黙の殺人者”については、2012年5月17日の院長ブログ
ウデをまくろう、ニッポン!5月17日「世界高血圧デー/高血圧の日」にアクセスを!
「塩を減らそうプロジェクト」では、
分かりやすく「塩」と「高血圧」のことを考える啓発活動を行なっています。
「塩と高血圧」講義
・塩の摂りすぎは、高血圧の主な原因!
・食塩摂取量の多い日本人
・高血圧ってなに?
・高血圧がもたらす病気
・血圧を下げる3つのポイント
サイト内は、基本的な血圧の知識を確認できるだけでなく、「食事で減塩!コンテンツ」の内容には、「食べたものを入力するだけで、塩分量・栄養バランスを計算!」、「自宅でカンタン減塩レシピ集」といった考えることができる、学習できるサイト構成となっており、多くの方にチェックして頂きたい内容となっています。
「塩を減らそうプロジェクト」や「ウデをまくろう、ニッポン」など「高血圧」のことを考える啓発サイトは、一般の方に理解しやすい言葉やコンテンツで構成されています。
「特定検診」や「職場検診」で血圧異常高値を指摘された方は、医療機関に行くことはもちろん大切な事ですが、自身で血圧について学習し、自己管理をしていく事も重要です。血圧が気になる方は、ぜひサイト確認してみて下さい。
TIPS
「啓発」と「啓蒙」言葉の使い方。
以前出席した東京でのある「慢性腎臓病対策会議」の議論の中、「啓蒙」という言葉は、悪意で使う人は先ずいないと思いますが、「蒙」の意味は、「無知なこと」をさすことから、「啓発」と表現するべきであることを確認しました。
何気なく使われている「啓蒙」という言葉について確認してみました。
「広辞苑」によると、
啓蒙:無知蒙昧(むちもうまい)な状態を啓発して教え導くこと。
無知蒙昧(むちもうまい):才知や学問のないこと。愚かで文字の読めないこと。また、その人。
啓発:知識をひらきおこし理解を深めること。
以上の解説からも「啓蒙」という言葉は、公的立場で仕事を行なう医療者や官公庁では控えるべきであり、「啓発」とすべきことが理解できます。
関連サイト
塩を減らそうプロジェクト
血圧ドットコム
24時間蓄尿検査「ユリンメート®P」について
日本腎臓学会は「CKD診療ガイド2012」を6月1日に発表しました。
慢性腎臓病患者の目標血圧管理も改訂されました。
これまでは「蛋白尿1g/日以上の場合、目標血圧は125/75mmHg未満」でしたが、
「全CKD患者の診察室目標血圧が130/80mmHg以下」に改訂されています。
◇降圧薬の第一選択は、糖尿病および0.15g/gCr以上の蛋白尿を有する患者では、
ACE阻害薬・ARBを第一選択。
◇蛋白尿が0.15g/gCr未満で、糖尿病でない患者の場合、
降圧薬の種類は問わないこととしています。
◇高度蛋白尿(0.50g/gCr以上)を呈する若年や中年患者では、
ACE阻害薬・ARBの使用を勧めています。
◇高齢者の場合は慎重な降圧を求め、140/90mmHgを暫定目標に降圧し、
腎機能悪化や虚血症状がないことを確認後、130/80mmHg以下へ降圧としています。
そして、食事療法は、慢性腎臓病管理の中で重要な要素となります。
基本事項は、
① 必要エネルギーを確保する(*1)
② たんぱく質を控える(*2)
③ 塩分を控える(食塩摂取量の基本は3g/日以上6g/日未満)
④ カリウムを控える(*2)
*1 肥満がある場合は、制限します。
*2 腎機能の低下の程度(病期)により指示量が異なります。
今回は、上記①〜④の項目の中で③塩分を控えるについて確認してみます。
日常診療で管理栄養士に塩分制限6g/日未満!の指示をし、栄養指導を行なっています。
外来では、24時間蓄尿検査を実施し、適切な食事管理が実行できているか確認します。
WEBサイト上では、「塩を減らそうプロジェクト」という団体が設立されています。
2010年1月に設立、代表顧問は、荒川規矩男先生(福岡大学 名誉教授、日本高血圧協会 理事長)です。余談ですが、荒川先生には、福岡大学において臨床及びベッドサイド講義で大変お世話になりました。
プロジェクトでは、治療の基本である、「一、に減塩、二、に運動、三、に薬物治療」をもとに、塩の摂取を減らすとともに、塩を体外に排出することで、体内減塩化を図ることの重要性を啓発しています。
日本では約4,000万人いるといわれる高血圧は、サイレントキラー ※であるために早期治療が行なわれず、放置された終末像としては、脳卒中・心筋梗塞・人工透析を必要とする慢性腎臓病などを合併します。高血圧を引き起こす主な要因の一つに、食塩の過剰摂取が挙げられています。世界的に食塩摂取量が多い日本人は、減塩のための工夫が必要です。
※ サイレントキラー:“沈黙の殺人者”については、2012年5月17日の院長ブログ
ウデをまくろう、ニッポン!5月17日「世界高血圧デー/高血圧の日」にアクセスを!
「塩を減らそうプロジェクト」では、
分かりやすく「塩」と「高血圧」のことを考える啓発活動を行なっています。
「塩と高血圧」講義
・塩の摂りすぎは、高血圧の主な原因!
・食塩摂取量の多い日本人
・高血圧ってなに?
・高血圧がもたらす病気
・血圧を下げる3つのポイント
サイト内は、基本的な血圧の知識を確認できるだけでなく、「食事で減塩!コンテンツ」の内容には、「食べたものを入力するだけで、塩分量・栄養バランスを計算!」、「自宅でカンタン減塩レシピ集」といった考えることができる、学習できるサイト構成となっており、多くの方にチェックして頂きたい内容となっています。
「塩を減らそうプロジェクト」や「ウデをまくろう、ニッポン」など「高血圧」のことを考える啓発サイトは、一般の方に理解しやすい言葉やコンテンツで構成されています。
「特定検診」や「職場検診」で血圧異常高値を指摘された方は、医療機関に行くことはもちろん大切な事ですが、自身で血圧について学習し、自己管理をしていく事も重要です。血圧が気になる方は、ぜひサイト確認してみて下さい。
TIPS
「啓発」と「啓蒙」言葉の使い方。
以前出席した東京でのある「慢性腎臓病対策会議」の議論の中、「啓蒙」という言葉は、悪意で使う人は先ずいないと思いますが、「蒙」の意味は、「無知なこと」をさすことから、「啓発」と表現するべきであることを確認しました。
何気なく使われている「啓蒙」という言葉について確認してみました。
「広辞苑」によると、
啓蒙:無知蒙昧(むちもうまい)な状態を啓発して教え導くこと。
無知蒙昧(むちもうまい):才知や学問のないこと。愚かで文字の読めないこと。また、その人。
啓発:知識をひらきおこし理解を深めること。
以上の解説からも「啓蒙」という言葉は、公的立場で仕事を行なう医療者や官公庁では控えるべきであり、「啓発」とすべきことが理解できます。
関連サイト
塩を減らそうプロジェクト
血圧ドットコム
24時間蓄尿検査「ユリンメート®P」について
Posted by 松山医院大分腎臓内科 at 03:34
│腎臓内科に関する事